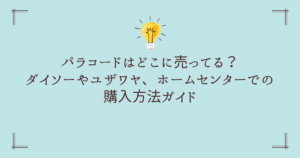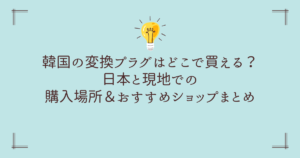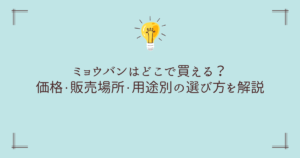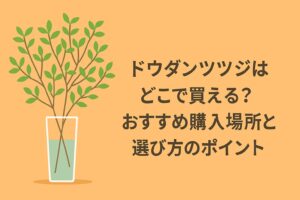聴覚過敏マークが必要だけど、「どこでもらえるの?」って意外と情報が少なくて不安になりますよね。
この記事では聴覚過敏マークはどこでもらえるのか、調べてわかったことをまとめています。
- 聴覚過敏マークはどこでもらえるのか、自治体の対応状況がわかります
- 自宅で印刷できるダウンロード方法や申請手順も詳しく紹介
- 100均グッズを使った自作アイデアや注意点もチェックできます
- キーホルダーやバッジ型の購入先や実際の使い方まで知ることができます
聴聴覚過敏マークはどこでもらえるのか?全国の自治体・配布先を調査!

全国の自治体では、感覚過敏のある方への配慮として「聴覚過敏マーク」や類似の意思表示マークを配布しています。どこでもらえるかを自治体ごとに調査しました。
- 聴覚過敏マークはどこでもらえる?市区町村の対応状況まとめ
- 公式サイトからダウンロードできる?
- 100均や自宅プリンターで自作はできる?
- キーホルダーやバッジ型の入手方法
- どんな人がつける?対象となる症状や使うメリットを紹介
聴覚過敏マークはどこでもらえる?市区町村の対応状況まとめ
聴覚過敏や発達障害など外見からは分かりにくい困りごとを示す意思表示マークは、「ヘルプマーク」などと併せ、全国の市区町村で無償配布されています。
多くの自治体では福祉課や障害福祉担当窓口、保健センター、市民センターなどで直接手渡し対応しており、自治体によっては郵送申請にも応じています。
特に、東京都は都営地下鉄やバス営業所でも配布を行い、利用者の利便性を高めています 。
新潟県など一部自治体では、ヘルプカードを併せて提供し、裏面に「声をかけてほしい内容」を記入できるなど実用性にも配慮しています 。
公式サイトからダウンロードできる?
多くの自治体や団体では、インターネットを通じて聴覚過敏マークを公式にダウンロード可能です。
墨田区では、「ヘルプシール」として聴覚過敏保護用シンボルをPDF・Word形式で無料公開。福祉窓口での配布と併せ、自宅で印刷して使うことが可能です。
また、株式会社石井マークが提供する「聴覚過敏保護用シンボルマーク」は公式サイトでPNG形式の無償データが公開されており、利用者は個人使用の範囲で自由にダウンロードし、印刷やカード・シールへの活用が認められています 。
このマークは、発達障害や感覚過敏者の「苦手な音」を可視化し理解促進に役立つデザインとしてSNSや支援コミュニティで広く注目されています。
加えて、新潟県をはじめ多くの自治体では、ヘルプマークやカード類を公式サイトからダウンロードして印刷・使用できる環境を整備しており、該当する市町村の窓口問い合わせ一覧もPDFで公開されています。
▼本当に聴覚過敏なの?という疑問をお持ちの方はこちら

100均や自宅プリンターで自作はできる?
多くの支援団体や有志によって提供されているテンプレートを使えば、「聴覚過敏マーク」は100円ショップの素材やご自宅のプリンターで自作可能です。

感覚過敏研究所(かびんの森)は、動物キャラクターを用いた「聴覚過敏マーク」のPNG画像データを販売していますが、個人であれば紙に印刷して缶バッジやシールに加工して使うことができます。
たとえば、100円ショップで購入した無地缶バッジキットや透明シール用紙を利用し、自宅のカラープリンターで印刷したマークを貼り付けてオリジナルのバッジやステッカーに加工する方も多く、SNSや支援サイトでは実際にイヤーマフやリュックに貼った写真が多数見受けられ 。
さらに、石井マークが企業として保護用シンボルマークを無償公開しているため、公式配布マークを正規にダウンロードして自作材料として利用できます。
個人利用に限られますが、自由にリサイズ・印刷して日常に取り入れるのに十分な高解像度データが揃っています。
ただし、自作する際は著作権の取り扱いに注意が必要です。感覚過敏研究所や石井マークの資料には「個人使用のみ」「営利目的の再配布・販売は禁止」と明記されています。
そのため、家庭用に印刷する範囲で楽しめば問題ありません。
キーホルダーやバッジ型の入手方法
多くの支援団体やクリエイターが、「聴覚過敏マーク」をキーホルダーや缶バッジ型グッズとして販売しています。
感覚過敏研究所のオンラインストアでは、聴覚過敏キャラクター「かびんの森のウサギ」が描かれた直径44mmの缶バッジが販売され、バッグやデスクに付けられる仕様です。
価格は約680円で、累計20,000個以上出荷されており、実用性と啓発効果を両立したアイテムとして支持されています 。
ハンドメイド通販サイト「minne」では、漢字・ひらがなバージョンのアクリルキーホルダーや缶バッジが出品され、平仮名バージョンは1,500円程度、漢字バージョンも同価格帯で購入可能です。
Mercari(メルカリ)などフリマアプリでも多数流通しており、片面のみのキーホルダー2個セットが約950円で出品されることもあります。
どんな人がつける?対象となる症状や使うメリットを紹介
聴覚過敏は、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)など発達障害を抱える人によく見られ、約25%前後の高い割合で報告されています。
また、てんかんや片頭痛、うつ病などの精神疾患が原因で聴覚過敏を引き起こすケースもあり、精神障害者保健福祉手帳の対象にも該当する可能性があります。
このマークは「音への配慮が必要な状態」を視覚的に表すことで、周囲の理解と支援を促す役割があります。
聴覚過敏保護用シンボルマークを掲示している人の多くは、公共交通機関や学校、病院での突然の音によるストレス緩和や、無用な誤解(=イヤーマフ=音楽鑑賞)を避ける効果を報告しています。
実際に、感覚過敏研究所の調査では、「感覚過敏マークをつけたことで、自分の困りごとが周囲に伝わりやすくなった」という体験談が多く寄せられ、「外出の勇気が出た」「理解者が増えた」という声も挙がっています。
特に、子どもや大人問わず、生活の質を上げる一助として実用性が高いと評価されています。
▼聴覚過敏の対処法はこちら

聴覚過敏マークはどこでもらえるか実際に調査してわかったこと
配布の実情や使用経験者の声から、聴覚過敏マークの申請や活用におけるポイントを整理しました。トラブル回避のためのヒントも紹介します。
- よくある質問まとめ|費用・有効期限・外出時の使い方など
よくある質問まとめ|費用・有効期限・外出時の使い方など
- 聴覚過敏マークの取得に費用はかかりますか?
-
ほとんどの自治体が無料で配布しており、福祉課窓口や郵送、PDFダウンロードも費用ゼロです。感覚過敏研究所が提供する缶バッジ型・データ版マークは個人利用向けで、ダウンロード版が680円で購入できます。
- 有効期限はありますか?
-
自治体配布のマークに期限はなく、一度取得すれば継続使用可能です。感覚過敏研究所のダウンロード版も「無期限」と明記されており、缶バッジ製作用データは一度の購入で使い続けられます。
- 外出時はどこにつけるのが適切ですか?
-
リュックや衣類の肩位置、バッグの外側に取り付けるのが一般的。イヤーマフやヘッドホンに貼るシールタイプも人気で、「苦手な音があります」と視覚で伝える効果があります。
- 公共交通機関や施設でも認識されていますか?
-
実例として、JR西日本の優先席周辺ではヘルプマークや感覚過敏マークを見かける利用者もおり、付けていることで「休憩許可」が得られたケースも報告されています
まとめ 聴覚過敏マークはどこでもらえる?
ここまでの内容を簡単にまとめると、「聴覚過敏マークって意外といろんな方法で手に入るんだな」というのが正直な感想です。
配布先や使い方もバリエーションがあるからこそ、自分に合った方法で手に入れて、少しでも過ごしやすくなるといいですよね。
ポイントを絞ると以下の通りです。
- 多くの市区町村では福祉窓口などで直接マークを無料配布しています
- 墨田区や新潟県などでは公式サイトからPDFでダウンロードも可能です
- 100均のグッズとプリンターがあれば、自作して使うこともできるんです
- 石井マークや感覚過敏研究所ではバッジやキーホルダーが購入できます
- 対象は発達障害や精神疾患のある人で、周囲への配慮を促す効果が大きいです
「苦手な音がある」ことって、なかなか言葉で伝えにくい。でも、こうしたマークがあると、それだけで少し気持ちが楽になることもあると思うんです。
自分を守るためにも、そして周りと気持ちよく過ごすためにも、使えるものは遠慮なく使っていきましょう。
参照元