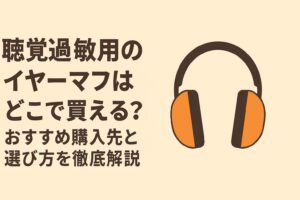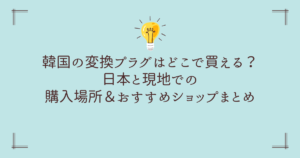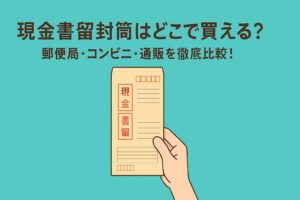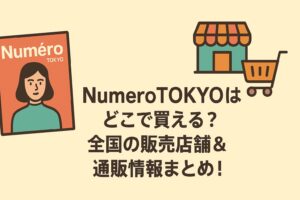聴覚過敏で「人の声まで消えるんじゃ…?」と不安。でも、実際にイヤーマフを使ってみたら違いました。
聴覚過敏のイヤーマフで人の声が気になる人にこそ、この記事を読んでほしいんです。あなたの生活が、ちょっと楽になるヒントがあるかもしれませんよ。
- 聴覚過敏のイヤーマフで人の声は本当に聞こえる?気になる遮音バランスを解説
- 高遮音イヤーマフの「中の構造」と「どの音域をカットするのか」が理解できる
- 耳栓との違いや、聴覚過敏の人がなぜイヤーマフを選ぶのか理由がわかる
- 通勤・学校・仕事…それぞれの場面で失敗しないイヤーマフの選び方がつかめる
聴覚過敏のイヤーマフで人の声はどこまで聞こえる?遮音構造と仕組みを解説
聴覚過敏に悩む方にとって、イヤーマフでどこまで「人の声」を遮れるのかは気になるポイントです。ここでは遮音の仕組みや、イヤーマフと耳栓の違いについて詳しく解説します。
- 人の声は聞こえる?遮音性能と会話への影響とは
- 遮音性の高いイヤーマフの仕組みと音域カットの関係
- 耳栓との違いは?イヤーマフが選ばれる理由
- 音を「遮る」と「やわらげる」の違いを理解しよう
人の声は聞こえる?遮音性能と会話への影響とは
イヤーマフはすべての音を完全にシャットアウトするのではなく、「不快な音の刺激を和らげつつ、会話ができるくらいは残す」のが基本設計です。
たとえば3M PELTOR H10Aは中音域(人の声が多く含まれる500〜2000Hz帯域)で約43.4dBもの遮音を実現し、電車や人混みのざわめきはしっかりカットしつつ、会話の内容までは潰さない絶妙なバランスを持っています。
また、実際に聴覚過敏に悩む方の声を聞くと、「周囲のざわめきが気にならず、でも相手の声はちゃんと届くので安心できた」という声が多数報告されています。
つまり、イヤーマフは「人の声を完全に消す」のではなく、「うるさい音を抑えて、コミュニケーションを保ちながら安心できる環境を作る」道具。
これが、聴覚過敏の方が日常で選ぶ大きな理由になっています。
▼イヤーマフのおすすめの製品などはこちら
▼イヤーマフ以外の聴覚過敏の対処法

遮音性の高いイヤーマフの仕組みと音域カットの関係
イヤーマフの遮音効果は、カップ構造と内部素材による周波数ごとの音の「吸収・反射制御」に基づいています。特に低音から高音まで幅広い帯域をバランスよくカットし、必要な会話音はほどよく残す設計が主流です。
二重構造カップによる広帯域遮音
3M製の高性能イヤーマフ(例:Peltor XシリーズやHシリーズ)は、外側・内側の二重カップ構造を採用することで、125Hz(低音)から8000Hz(高音)まで安定した遮音性能を実現しています。
たとえばPeltor X5Aは、125 Hzで約23.9 dBカット、1000 Hzで約43 dBカットという特徴的な性能を持ち、NRR値30 dBという高い指標を誇ります。
吸音材とスペーサーによる音質調整
カップ内部には吸音材が詰められており、反射を減らして生命帯域の音をまろやかにします。
JVCのEP‑EM70も、内蔵スポンジとクッションで「高音から低音まで安定した遮音性」を達成しています。これにより、子どもや聴覚過敏者でも会話音がうるさくならず、必要最低限の音だけが聞こえる設計です。
周波数ごとの遮音値指標:NRR・SNRとは?
遮音性能はNRR(ANSI基準)やSNR(JIS基準)で評価され、数値が高いほど強力に音をカットします。ただし「必要以上の遮音」はコミュニケーションの妨げになる可能性があります。
一般的にはNRR30 dB前後の製品が、騒音環境下でも会話を邪魔せずに保護するバランスが取れており、85 dB程度の騒音を事務所レベル(50 dB程度)へ下げる目安とされています。
耳栓との違いは?イヤーマフが選ばれる理由

耳栓は耳穴に直接挿入して高遮音(NRRで30dB以上)ながら、フィットの失敗や長時間使用で痛み・蒸れ・衛生面トラブルといった課題もあります。
一方、イヤーマフは耳全体を覆う構造で、遮音性能は25~30dB程度ですが、装着が簡単で圧迫感が少なく、耳穴を塞がないため長時間着用しても快適。
聴覚過敏のある方にも清潔で使いやすいと選ばれる理由となっています。
また、聴覚過敏の子どもや成人では、イヤーマフ使用で騒音ストレスが軽減され、生活の質向上が報告されており、医療現場でも補助具として広く活用されています 。
▼おすすめの耳栓はこちら

音を「遮る」と「やわらげる」の違いを理解しよう
音を完全に「遮る(block)」か、心地よく「やわらげる(attenuate)」かで使う用途や効果は大きく変わります。ここではその違いをわかりやすく整理します。
遮る(Block)
完全遮音に近い状態を目指す方法。耳栓や防音室のように音を物理的に止めるアプローチです。
音を完全に妨げることで安全性は高まりますが、会話や周囲の警報音すら聞こえなくなるリスクがあります。
- 耳栓はNRR(ノイズ低減値)が30〜33 dBと非常に高く、低周波も効率よく遮りますが、社会的コミュニケーションが取りづらくなることもあります 。
- 完全遮音イヤーマフは存在せず、最大でも約30 dBまでのNRRが多く、遮音領域に限界があります 。
やわらげる(Attenuate)
イヤーマフに多く見られる設計で、イヤーマフ内部の吸音材やカップ構造で音を和らげます。特定の帯域を抑えつつ、人の声や必要な環境音は残すバランスが特徴です。
- 実際の遮音値は25〜30 dB程度で、装着ミスの影響も少なく、使用者の耳に合った状態で安定した性能を発揮します 。
- NRR表記が最大でも30〜33 dBでも、現場では50〜75%の性能しか発揮できずに、「やわらげる」効果になることが多いです 。
なぜ「やわらげる」が聴覚過敏には向いているのか?
- 会話が可能:相手の声や重要な音は確保しつつ、雑音だけを抑えるのでストレスが少ない。
- 安全性:警報音や周囲の声が消えないため、状況判断ができる。
- 実用性:使いやすく、長時間の着用も耐えやすい設計で、継続使用に向いています。
▼聴覚過敏の方の関連記事


聴覚過敏のイヤーマフで人の声が気になる人へ|選び方と使用感のリアル
聴覚過敏の人にとって「どのイヤーマフが合うか」は生活の質に直結します。ここでは使用感や用途別の選び方、よくある悩みへの対処も紹介します。
- 通勤・職場・学校などシーン別の選び方のポイント
- よくある質問とトラブル例|「外せと言われたらどうする?」など
通勤・職場・学校などシーン別の選び方のポイント

イヤーマフを利用する場面によって「快適さ」「目立ちにくさ」「遮音性」のバランスが変わります。ここでは、実際のデータや体験談をもとにシーン別の選び方を紹介します。
通勤/公共交通機関での使用
通勤中はエンジン音や踏切音などの騒音と、周囲の会話の両方が発生します。
「ノイズキャンセリングイヤホンよりも環境音を幅広く遮るため、話し声などが気になる場合はイヤーマフが有効」という提言がありますが、着脱時に中の空気音(ゴーッという音)がすることもあると報告されています。
職場での活用
オフィス環境では小さなタイプのイヤーマフやデザイン性に配慮された製品が好まれます。
dodaの調査でも「イヤーマフはファッションや音楽用と誤解される場合もあるため、使用前に職場へ相談すると安心」とアドバイスされています。
また、仕事中に「車や機械の騒音は抑えたいが、同僚の声や電話音は拾いたい」という場合には中音域の調整機能付き製品が向いています。

学校での活用
聴覚過敏の子どもが教室でイヤーマフを使う場合、「理由と必要性を先生やクラスに事前説明すると理解が深まりやすい」という実例が多数あります。
また、学校では「静けさ」は歓迎されますが、「ずっと付けていると逆に慣れすぎて着けたくないと感じる場面が減る」可能性もあるので、着脱のタイミングをつくることが重要とされています 。

シーン別イヤーマフ選びのまとめ
| シーン | 重視ポイント | 製品の特徴 |
|---|---|---|
| 通勤/公共交通機関 | 騒音カット・折り畳み | 二重カップ式、NRR高め、携帯性あり |
| 職場 | 目立たず通話対応 | スリム構造、中音強調タイプ |
| 学校 | 周囲への配慮・着脱のしやすさ | 軽量、シールやバッジで理解促進、着脱しやすい設計 |
よくある質問とトラブル例|「外せと言われたらどうする?」など
- 職場や学校で「外せ」と言われたらどうすればいい?
-
医師の診断書や「合理的配慮シート」を提示し、正式に理解を得るのが効果的です。
厚生労働省でも「耳覆い/耳栓は、作業特性に応じて使用を検討すべき」と明記されており、実務でも労働環境に応じた使用が認められています。まずは医師の判断を受け、学校や職場へ相談しましょう。 - 周囲から「目立って恥ずかしい」と言われたら?
-
「感覚過敏相談シート」や「配慮依頼の付箋」を活用し、周囲へ適切に説明しましょう。
実例として、支援施設では「イヤーマフ使用中、声かけは前からお願いします」と付箋で案内を置いたケースもあり、配慮と相互理解が進んでいます。また、感覚過敏マークを導入する学校・職場も増加中です。 - 過度に装着し続けると依存や耳への負担は?
-
過度使用による依存感や汗による肌トラブルなどが一部の利用者で報告されています。
ASDの子ども13名の調査では、69%が肯定的評価ながら、31%に「依存や不安」、23%に「汗疹・外耳炎」といった症状の実例がありました。家庭や学校では「外す時間」を設ける配慮が推奨されます。
まとめ 聴覚過敏のイヤーマフで人の声は?
ここまでの内容を簡単にまとめると、聴覚過敏の人が「人の声がどう聞こえるのか」「イヤーマフで本当に楽になるのか」と悩むのは、とても自然なことだと思います。
ポイントを絞ると以下の通りです。
- イヤーマフは人の声を完全に消すのではなく、ざわめきを抑える働きをする
- 遮音性能はNRRやSNRで確認でき、30dB前後が日常使用に向いている
- 耳栓よりも圧迫感が少なく、装着や着脱が簡単で衛生的に使える
- 通勤・職場・学校など、シーンに合った選び方が大事になってくる
- 医師の診断書や合理的配慮の理解を得ることで、周囲との摩擦も減らせる
もし今、少しでも「人の声は大丈夫かな?」と不安に思っているなら、一度イヤーマフを試してみるのもアリだと思います。